 プロの方ページ | 栽培情報 | 肥培管理 | 栄養素 N-P-K-Ca-Mg-S-Cl
プロの方ページ | 栽培情報 | 肥培管理 | 栄養素 N-P-K-Ca-Mg-S-Cl
シクラメンの施肥について決定するために、まず一番大切なのは気候および)根に供給される空気と水です。
これらの要因は、バランスの取れた施肥を行うために影響します。
施肥の定義
COMIFER(フランス[植物]施肥推論委員会)の見解では、分けて考えなければいけない概念が少なくとも2つあります。
栄養素へのニーズはある要素が株によって吸収された量です。これは、目的を達するために必要であり十分な量です。
全てのシクラメン品種が同じように周囲の環境から栄養素を摘出できる力を持っているとは限りません。
中には、「要求の多い」品種という、周囲の環境からの栄養素の取り入れ割合が低いものもあります。
この「要求の多い」品種は、従来の栽培法に使われていたより、より多くの堆肥を与えることによって、施肥後の「反応」(生長も含む)を顕します。
シクラメンを含む球根植物はリンと微量要素を多く必要と分類されています。
窒素:(生長生育)の主な要因
窒素は、水の次に株の生育のために必要な要因です。そして、根によって吸収される要素のなかでも量的に大きな割合を占めます。
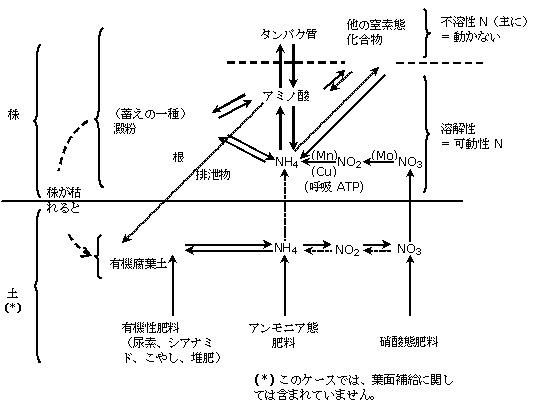
根の窒素吸収は、イオン吸収によって行われます。
窒素のイオン形態は2つあります:
アンモニア態窒素と硝酸窒素、この主な2つの無機要素の栄養としての役割は、下記の要因で変化します:
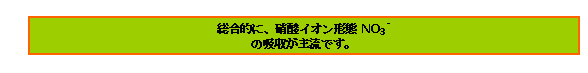
注意::
全てのシクラメンでは、有機体でも小分子状態なら少量は有機性窒素を吸収できます。しかし、これは他の取り入れと比べると非常に少ない量になります。尿素の葉面散布は、有機窒素吸収に有効なので重要です。
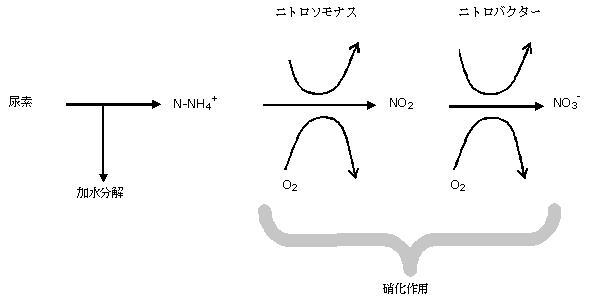
尿素は加水分解でアンモニア態窒素となり、硝化されてシクラメンが吸収できる形態、硝酸態窒素になります。
尿素が加水分解する速度は様々で、コントロールも難しいです。
有機物質の分解プロセス:空気をたくさん含んだ、あまり酸性でない用土内でのバクテリア活動により行われます。
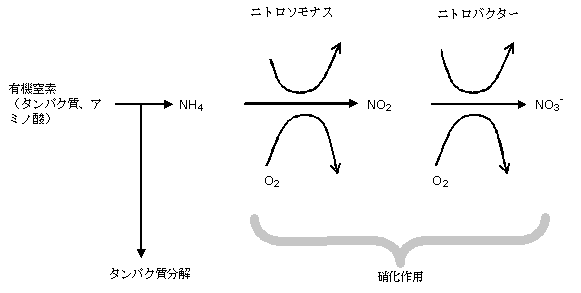
図が示すように、有機窒素を使用するには様々な外的要因に支配されており、利用可能な窒素を得るにはタイミングに左右されます(温度、酸素など)。-(たい肥、有機質窒素肥料を使用した場合)
アンモニア態窒素は、陽イオンです:NH4+。そのため、CECに固定され、CECに固定されたNH4+ と水溶液内のNH4+ の比率は、1:1に固定されます。この比例はピート主体の用土に適応でき、流亡による窒素損失をくいとめます。いくつかの物質(ゼオライトなど)はアンモニア態窒素に対し強い親和性を持ち、十分に貯蔵でき、強い「遅延効果」を発揮します。
しかし、アンモニア態窒素の発生は、一番好ましくない状況(有機物質の分解が活発な状況で起こることがあります)下に養液に溶出するのでご注意下さい。
温度、酸素など標準状態下で生育されたシクラメンは、栄養素を独自で調整、コントロールすることができます。硝酸態窒素は適度に利用されます。
しかし、特に根の部分(酸素と温度)がストレスにさらされたシクラメンは積極的に吸収を行わなくなり、吸収は受身になります。そうすると、アンモニア態窒素は過剰に摂取されることにもなり、アルカリ性に傾きすぎた特化した樹液によって中毒を起こします。
例:
鉢上げとアンモニア中毒
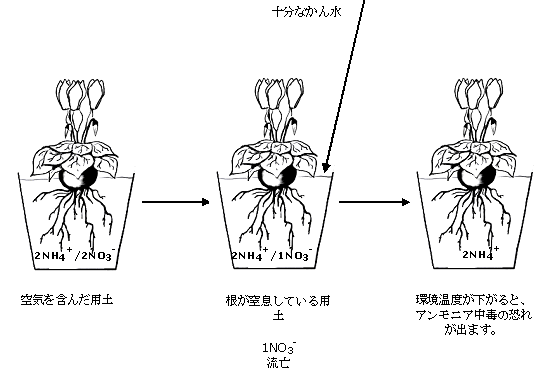
PGミックスを混ぜたばかりのピート主体用土のN-NO3 : N-NH4比率は、水溶液では1:1に近くなります。
鉢上げ時期に、少し流出するくらいの「良いかん水」は、一部の硝酸態窒素を流亡させますが、流亡しにくいアンモニア態窒素は養液内に残ります。
用土が乾かないうちに2度目のかん水を行うと、弊害が起きます。用土内の酸素欠乏から根が窒息状態に陥り自己調整が利かなくなり、硝化作用が妨げられます。
栽培途中に用土を分析した際、アンモニア態窒素の比率は低くなくてはいけません。
硝化作用がきちんと行われているということは、気層が確保されている土です。
アンモニア態窒素はpHが高いと障害の発生が心配されます。
しかし、pHが低く、酸性の環境では、アンモニア態窒素による阻害でカルシウム吸収速度が低下します。
硝化作用は、低い温度環境ではあまり活動的ではなくなります。そして、光が弱い環境でも同じように硝化作用が低下します。そこで、肥料内のアンモニア態の比率(または、尿素の比率)を低くすることをお勧めします。
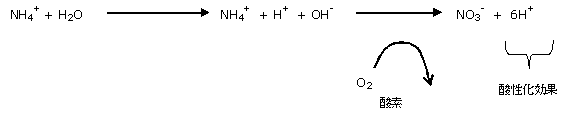
アンモニア態窒素から硝酸態窒素への硝化過程では一時的な酸性化作用が生じます。この酸性化作用は「弱い」ものです。
アンモニア態窒素のこの酸性化効果は、この場合、有機用土のpHを下げるためにではなく、pHを安定させ、pH上昇を防ぐためです。
硝化作用の酸性化効果は、重炭酸塩などを足した場合のアルカリ化に比べ、まだ弱い作用となります。
逆に、無添加の環境では、酸性化作用は養液のpH調整として現実的な方法です。
硝酸態窒素は陰イオン:NO3- です。すなわち、CEC(陽イオン交換容量)に固定されていないということです。
これは、すなわち、流亡の可能性があるということです。
硝酸態(窒素)肥料のみの施肥の場合、用土のpHが上昇します。
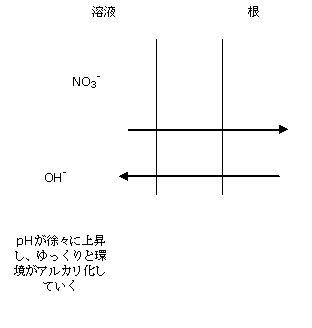
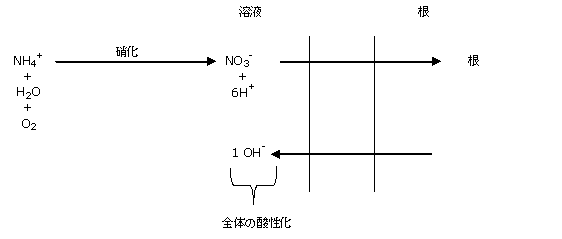
そこで、常にアンモニア態窒素を全ての肥料に混ぜておくことをお勧めします。
窒素は発育の旺盛さと植物の生育にとって必要不可欠なものです。
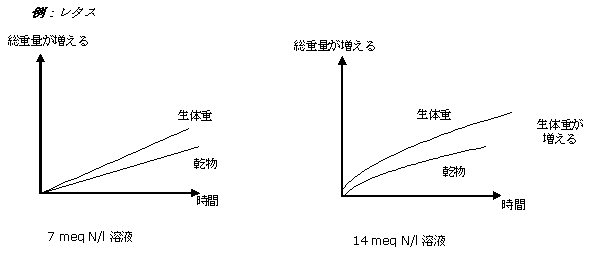
もちろん、硝酸塩は乾物の生産を促進させます。そしてそれ以上に、花や貯蔵部分の重量が増加します。
この例では、窒素、および硝酸塩の添加は乾物の増加は助長しませんが、総重量を増やします。これは希釈として知られている現象で、シクラメンでは葉の肥大の原因として知られています。
どのようにして根への利用可能な硝酸塩が増えることが水の蓄積を促進し、株の総重量の増加へ貢献しているのでしょか?
根での硝酸塩の存在によりシクラメンにとって利用可能な水がふんだんにあることによって、シクラメンの液胞がふくれ、細胞の膨張を助けます。その結果、柔らかく凍結に弱くなります。
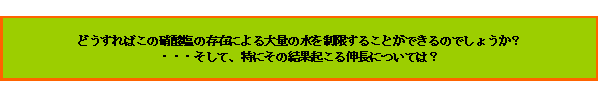
第1の方法:
窒素対カリウムの比率、N / K2Oはカリウムが有利になるようにならなければなりません。カリウムは、窒素を「エスコートする」(付き添う)「騎士陽イオン」と覚えて下さい。
実際に、カリウムは少なくとも窒素と同じくらい、またときには窒素より多く消費されます。
そして、カルシウムとマグネシウムに比べ吸収されやすくなっています。
その上、カリウムの組織内での主な存在形態はイオン状態:K+(水和物)。
そこで、マイナス電荷を中和させるためのプラス電荷を補充することになります。
すなわち、硝酸塩の還元によりできた有機酸を中和することになります。
このように、硝酸塩の蓄積によって起こる「水の取り込み」は、カリウムによって止められます。
その上、カリウムは蒸散を調整する役目、すなわち水の取り込みを調節する役目を持っています。
カリウムは、伸長や凍結への弱さなどをもたらす窒素の作用を釣り合わすために必要な陽イオンです。
第2の方法:
塩類濃度を上げて発育の旺盛さをコントロールします。
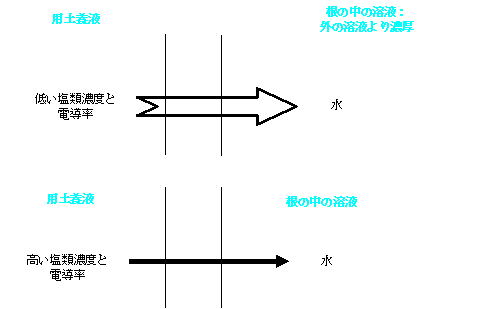
水は常に濃度の低い環境から高い環境へ移動します。そこで、用土養液の塩類濃度が上がると根を通じる水の流れは少なくなります。
塩類過多による生理学上の乾燥をシクラメンに起こすことができることが分かります。
用土内塩類の主要素はまだなお窒素です。
窒素濃度を上げることによって塩類濃度を上げ、水の流れをコントロールする方法は扱いにくいテクニックですが、適した用土を使用することによってリスクを下げることができます。
しかし、この方法は球根と根基部に、寄生性真菌類による病気を生じさせやすくなるので、シクラメンにはお勧めできません。
カリウム:陽イオンの親分
「酸化」という表現は、栽培学上K2Oには適切ではないですが、下記のように肥料を表す際に使われます。
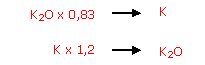
水溶液内の養分は電解質、K+の形で、それに陰イオンを伴って存在しています。
用土内のカリウムのいくらかはCECに吸収され、その割合は変動します(上記参照)。
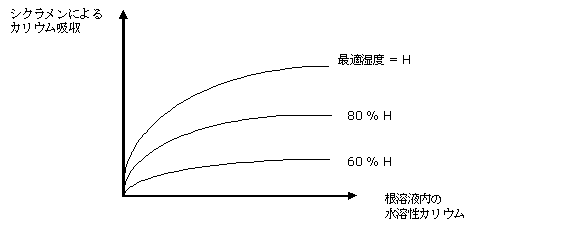
用土内の湿度が最適なら、それだけよくカリウムを同化できます。
このようにして主に「乾いた」栽培パターンではカリウムの吸収が少なくなると言えます。そこで、カリウムの比率を上げることが必要です。
実際、硝酸塩、リン酸塩、硫酸塩などとしてカリウムを施肥しても、CECはカルシウムとマグネシウムが優先されています。
したがって、カリウムは養液へ陰イオンを与えても溶出することはほぼありません。
水の移動が根の中で充分なカリウム濃度を保つ役目をしています。有機用土での陽イオン供給をコントロールするには、K : Ca + Mg 比率は最適な方法ではありません。
そこで、用土養液内に適切なカリウム濃度を保つと同時に、カリウムの好ましい「吸収」のため、カリウム供給をできるだけ分散する必要があります。
ほとんどのシクラメン品種は、下記の段階で自然にカリウム消費が増えます:
以上の時期ではカリウムの消費(または、根から株へ移動する)量は窒素の3~4倍になります。
カリ肥料は吸収されやすいため、鉢土内のカリ濃度が高くなるとたまに「過剰吸収」になってしまいます。
この「過剰吸収」が細胞呼吸を刺激し、結果的に栽培学上:
しかし、もちろん呼吸係数の過剰にも注意しなければなりません。シクラメンのエネルギーを消耗させ、早期老化を招きます。
必要なのは、N:K2O比率を早期生長段階では1 : 2あたりに保ち、後に成熟前段階に1 : 3から1 : 5 まで上げていきましょう。
内部でのカリウムの必要性は日照時間(日差し)が増えると上がります。シクラメンは大幅に増えた放射エネルギーを最大限に利用しようとするからです(シクラメンの夏期栽培のケース)。
カリウム要求は冬期や日照時間が短い期間には減ります。シクラメンのカリウム消費は夏期よりも減りますが、少ない日差しを最大限利用するために余分なカリウム吸収を促すよう根へのカリウム供給を増やします。冬にはN:K2O比率は、1 : 3あたりがお勧めです。
原則として、栽培条件が悪くなればなるほどN:K2O比率がカリウムに傾くようにします。特に、用土の湿度と発根がきちんとコントロールされてない場合などがあげられます。
局部的なかん水は湿度の低下につながり、発根も湿った部分のみに集中します。用土内の水分張力はスプリンクラーシステムを使用した場合よりも弱くなります。
しかも、カリウムは用土内相対湿度が高い方が吸収されやすくなっています。
スプリンクラーや底面給水システムよりも、低いN:K2O比率でのドリッピング(点滴チューブ)かん水の方が適しています。
注意:スプリンクラーかん水システムは、衛生的な理由でシクラメンにはお勧めできません。
リンは、主に陰イオンの形 :HPO42- または H2PO4-で存在しています。用土内でのこの二つのリンイオンの比率は環境pHにより左右されます。
無水リン酸(P2O5)での表現の仕方は、机上の計算方法のみで、実際には吸収できません。
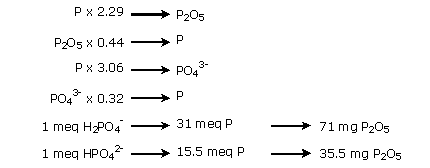
リンはpH 5.5 ~7.0 の環境で特によく吸収されます。
このpH値の間ではリンは主に用土内に存在し、陽イオンブリッジ(橋・リンク)によって固定されます。
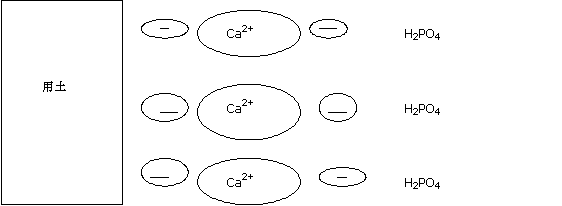
すなわち、この成分は有機用土ではほとんど溶出しないということになります。
ファイル1:生理学と栄養素 をご参照下さい。
主な相互作用は窒素とリン:N-P に関係しています。リンのより良い吸収のためには窒素の供給が不可欠です。特に気温が低い場合のアンモニア態リン酸塩肥料を与えるときはNが必要です。なぜならば、低温ではリンの吸収は悪く、NとPを組み合わせた形の肥料は、条件が悪い場合でもリンを最大限に活かすことができます。
注意:球根へ同化物質をきちんと運ぶには、スムーズなリンの吸収が必要です。
リンの主な対抗となるのが鉄と亜鉛です。主に、リン過多は鉄と亜鉛の吸収を止めます。しかし、緩衝能の高い用土で鉢物を栽培すると、この現象はあまり顕れません。
リンは、酸性の環境でモリブデン吸収を阻害します。そしてモリブデン欠乏を招きます。しかし、この現象も鉢物栽培ではほとんど見られません。
カルシウムは養液内ではCa2+イオンとして存在しています。カルシウムは、過剰イオンを調整し、若い細胞を補強するコンクリートのような役割のほか、細胞の浸透性を弱めます。
カルシウムは細胞発達の全てのステージにおいて役割を果たします。
pH の影響については ファイル2:CEC / カルシウム / 重炭酸塩 / pH の章で詳しく説明しています。
抽出した水から量ったカルシウムは、株に吸収されるカルシウムとはなんら相互関係がありません。
カルシウムの吸収は下記の4つの可変要素に左右されます:
品種が発育旺盛であればあるほど、株の必要性が高まります。水と窒素に対するカルシウムの役割は高まります。
カルシウムは大きな陽イオンなので株内を簡単に動き回れません。そこで、すぐに必要なカルシウムと窒素のニーズが釣り合わないことが起こる恐れがあります。
葉の縁のネクロシス(壊死)のリスクも高まります。
カルシウムは、用土が湿っている方がより吸収されやすくなっています。
塩類濃度が高くなれば、カルシウムの吸収が低下します。カルシウムが幼葉や花まできちんと到達するには、蒸散に至る植物内の流れが大きくなければいけません。高い塩類濃度は蒸散の流れを阻止してしまいます。
環境の(空気)湿度が高いほど、カルシウムは吸収されにくくなります。高い湿度は株内の蒸散の流れを弱めます。そうすると、カルシウムはうまく移動できなくなり、新しい細胞に届きにくくなります。
カルシウムがきちんと吸収されるためには用土はたくさんの空気を含み、低い湿度を保つことが必要です。
シクラメンは柔らかくなり、葉の縁のネクロシスに掛かったり、花の奇形が出たりします。
K とCa は拮抗します。シクラメンへのカルシウム供給の調整では、液肥のカリウムレベルを下げるか、かん水を少ない量で頻繁に行うことが必要になります。
Ca とMg は、鉢植えのシクラメン栽培の場合、あまり拮抗しません。ここでは、マグネシウムの供給をコンスタントに保つことが重要です。
カルシウムの吸収は、2月と10月のこの時期、低下します。シクラメンの自然な傾向としてカリウムを要求します。その上、相対湿度はしばしば高く、かん水パターンは理想的でない恐れもあります。
葉の縁のネクロシスの危険も出てきます。そこで、場合によってかん水パターンを短いものと長いものを使い分けることが必要になります。
マグネシウムの養液内での形態は、Mg2+イオンです。
マグネシウムはクロロフィル(葉緑素)分子に不可欠な一部です。そこで、マグネシウム欠乏は古い葉にクロロシスを及ぼします。
これは、以下の要因によってコントロールされています:
マグネシウムは根からの吸収に関しては、カルシウムとカリウムの中間くらいの反応を示します。
多くのマグネシウムの吸収は用土内部の酸素と相互に関連しています。
この大きな原子は、低い温度では吸収が悪くなります。
マグネシウムは、カリウムとカルシウムに拮抗しています。
土を使わない栽培で特に重要なことは、液肥内のマグネシウム濃度を常に通常レベルに保つことです。
ほとんどのマグネシウム吸収は水の状態(用土内湿度/ 空気の相対湿度/ 日差し)に管理されています。
硝酸態N-NO3- の窒素とマグネシウムは相互関係にあります。すなわち、硝酸態窒素の供給がマグネシウム吸収を促進させます。
硫酸はタンパク質およびにクロロフィルの合成に関与しています。硫酸欠乏が起こると、株の新しく成長している部分に変色が起き、可溶性硝酸が株に蓄積してしまいます。
硫酸と窒素の代謝は関係があります。
硫酸はSO4の形態で水溶液内に存在しています。これは硫酸塩の形態です。
SO4と窒素の相互作用があります。硫酸の供給が十分でないと植物体内窒素濃度が上がり、生産性(花数など)が下がります。これは繊維質の用土でよく見かけられる傾向です。
塩素は、主に乾物生産を調整し、蒸散にブレーキを掛ける役目をしています。
2565, rue de Montourey
83600 Fréjus - France
Tel (輸出部代表) : +33 (0)4 94 19 73 04
Tel (代表) : + 33 (0)4 94 19 73 00
Fax : +33 (0)4 94 19 73 19

